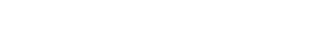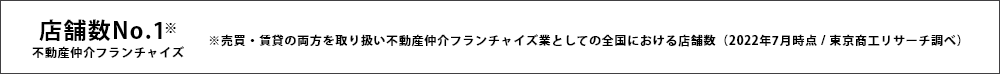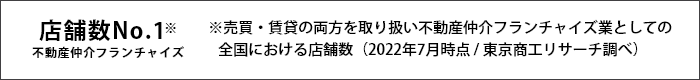「よっちゃんブログ」の記事一覧(244件)
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/06/27 16:24
相続クイズに答えてください。
Aさんは100坪の雑種地を所有しており毎年の固定資産税に頭を痛めています。
ではこの土地を持ち続けた場合何年で土地の価値がなくなるでしょうか?
ちなみにこの土地の路線価は坪20万円。
実際の売却価格は坪25万円、今後の地価上昇はゼロで推移します。
答え:あってますか?
この問題を解くために、固定資産税が毎年どのくらいかかるのか、
そしてその固定資産税の累積額が土地の価値と等しくなる年数を計算する必要があります。
まず、土地の価値を計算します:
- 土地の面積:100坪
- 実際の売却価格:25万円/坪
したがって、土地の総価値は:
次に、固定資産税の計算を行います。固定資産税は路線価を基に計算されますが、具体的な税率が必要です。
仮に固定資産税率が1.4%であると仮定します。
路線価に基づく土地の評価額:
年間の固定資産税:
最後に、固定資産税が土地の価値と等しくなる年数を求めます:
よって、約89年で土地の価値が固定資産税によってなくなる計算になります。
もし具体的な固定資産税率が分かれば、その税率を使って再計算する必要がありますが、
概算では89年という結果になります。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/06/26 16:06
(例)付言 事業承継
私は、亡き父から事業を引き継ぎ、今日まで遮二無二働いてきましたが、高齢にもなり体力が衰えたことを最近痛感しています。これからも事業発展のため、尽力するつもりですが、私の万一のことを考慮した結果、私と共に苦楽をともにした妻の生活を第一に、そして子どもたちのことを考え遺言を遺すことにしました。皆の生活基盤の充実を図るためにはどうしても会社経営について考える必要があります。
亡き父から事業を引き継ぎ、まがりなりにも事業は拡大できたと自負しています。
幸いにも○○が事業に参画し、従業員、お得意さまに信任も厚く安心して事業を引き継ぐことができます。一言述べるのであれば、会社経営は自分だけの問題ではなく、従業員には家庭があり、お得意様にも家庭がある。まして○○には自分の家庭を又○○家を守る責務があります。それには会社の発展がどうしても必要となります。どうか思慮深い経営者となることを期待しています。
○○、○○には財産分けが少なくなりましたが、先に述べたとおり、妻である○○の生活のこと、会社経営するためにはそれなりの資産の裏付けが必要なこと、ましてや、代々続いている○○家は今後とも未来永劫に発展していかなくてはならないこと等を勘案すると資産を分散させる訳にはいかないのです。どうか理解をお願いします。○○は以上のことを理解し、○○を大事にし、○○、○○と仲良くし、今後の援助をお願いします。妻の○○は影に日向に本当に良き理解者でした、ありがとうの言葉を遺します。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/06/26 14:53
(例)付言 思い
私の人生の晩年は子どもたち全員がよく判っているとおり、母さんと交互に入退院の繰り返しでした。皆がそのたびに力を合わせ看病に、生活の面倒にと頑張ってくれたことに感謝しています。
また、友人の皆さんから素晴しい子どもさんに成長し、親孝行なお子さまですねと言われるたびに嬉しく、親として立派に成長してくれたことに幸せを感じていました。ありがとう。
長男○○にお願いがあります。先に述べたとおり、晩年は近隣の皆さま、友人・親族に大変な迷惑をかけています。このご厚情に感謝しつつ良きお付き合いをお願いします。
少ない財産ですが、極力平等に財産分けすることとしました。子どもたち全員が私の宝です。どうか今までどおり仲良くし母を助け協力をお願いします。
家族・家の中心になる長男○○に次の言葉を遺します。常日頃から話しをしていた内容です。それが私の一番大切な遺言です。心に留めておいてほしい願いです。
人生は自分一人のためにあるのではない、自分が努力し、家庭が円満であれば、妹○○の家族も円満になる。親戚、友人が集まってくる。
自分の家が発展繁栄すれば妹の家族、親族も発展繁栄する。○○家一族の発展のために自分が何をし、何をすべきかよく考え行動すること。悪いことをすれば、家族、親族の全部が悪くなる。特段の注意をお願いします。また、親戚筋にはいかなる場合でも不義理してはならない、反対給付を期待してはならない、それが良い付き合いになる秘訣です。
(例)付言 事業承継
私は、亡き父から事業を引き継ぎ、今日まで遮二無二働いてきましたが、高齢にもなり体力が衰えたことを最近痛感しています。これからも事業発展のため、尽力するつもりですが、私の万一のことを考慮した結果、私と共に苦楽をともにした妻の生活を第一に、そして子どもたちのことを考え遺言を遺すことにしました。皆の生活基盤の充実を図るためにはどうしても会社経営について考える必要があります。
亡き父から事業を引き継ぎ、まがりなりにも事業は拡大できたと自負しています。
幸いにも○○が事業に参画し、従業員、お得意さまに信任も厚く安心して事業を引き継ぐことができます。一言述べるのであれば、会社経営は自分だけの問題ではなく、従業員には家庭があり、お得意様にも家庭がある。まして○○には自分の家庭を又○○家を守る責務があります。それには会社の発展がどうしても必要となります。どうか思慮深い経営者となることを期待しています。
○○、○○には財産分けが少なくなりましたが、先に述べたとおり、妻である○○の生活のこと、会社経営するためにはそれなりの資産の裏付けが必要なこと、ましてや、代々続いている○○家は今後とも未来永劫に発展していかなくてはならないこと等を勘案すると資産を分散させる訳にはいかないのです。どうか理解をお願いします。○○は以上のことを理解し、○○を大事にし、○○、○○と仲良くし、今後の援助をお願いします。妻の○○は影に日向に本当に良き理解者でした、ありがとうの言葉を遺します。
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/06/26 14:49
遺言書の付言とは
法律上の効果はないが、円満な相続、もめない相続を実現するための事実帖の効果があり大変有益です
付言は遺言書の中に残す「遺言者のメッセージ」
遺言書には残される家族に思いを伝える「最後の手紙」
大切なのは何をだれに残すのかダ家でなく「なぜそのように残すのか」
「なぜ遺言書を遺すのか」を伝える
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/06/26 14:45
公平に遺産分割できない方
相続人以外に財産を渡したい方
夫婦間に子供がいない方
後継者に事業を引き継がせたい方
相続人の中に行方不明者・認知症患者・多重債務者がいる方
前妻・前夫の間にこがいる方・婚外子がいる方
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/06/26 14:33
誰が行いますか?
・亡くなった人の財産や借金を調べて財産目録を作成する
・目録を元に相続人に財産内容を説明する
・相続税がかかるときは税理士と打ち合わせして納税資金を考えてどの財産をだれが相続するのか?を提案して話し合う
・分け方について相続人全員の合意を得て被相続人の戸籍・相続人全員の戸籍・印鑑証明を取得して遺産分割協議書を作成する
・その後、各相続人が預金口座の解約、不動産の 登記など名義を変更し相続税の申告納税を行う
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/06/22 08:48
遺言書は死後の遺産の扱いについて一定の方式に従って表示して文書のこと
民法では定められた法定相続より優先される
民法で定められた方式、軽視に従っていなければ無効となる
記載の仕方の注意点
記載する財産はだれが見てもわかる
建物は登記されている
遺言執行者の指定
現預金
予備的遺言
付言
カテゴリ:よっちゃんブログ / 投稿日付:2024/06/22 08:23
今日のニュースで紀州のドンファンと呼ばれ不審な死を告げた和歌山県の資産家の男性。
遺言書が見つかり「個人の全財産を田辺市に寄付」と記されていた。
親族側が裁判を起こしたが棄却され判決は遺言者が有効という主張が認められた。
というニュースが流れていました。
今回はおさらいとして遺言書作成について触れていきます
遺言書作成で大事なこと
・遺言書は残せは良いわけではなく内容が大事
・司法書士は決まったことをそのまま書くだけ
・出口を考えて相続人が困らないような内容で書くことが必要